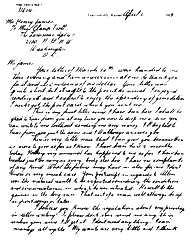カール・パンズラム

ヘンリー・レッサー
今回は極悪非道な殺人者と一人の看守との友情の物語である。涙なくしては読み進めることが出来ないので、予めハンカチを御用意願いたい。
時は1928年8月、ワシントンDC連邦拘置所での出来事である。4月に赴任したばかりの若い看守、ヘンリー・レッサーには気になる囚人がいた。大柄で、いつも無表情なカール・パンズラムという男である。
或る日、見回りがてらに何気なく訊いてみた。
「あんたの裁判はいつから始まるんだ?」
「11月だ」
その眼には凄みがあった。暗黒街の大物に違いないとレッサーは思った。
「娑婆では何をしていたんだ?」
「人間の更正だよ」
すると同じ房の囚人たちが笑い出した。レッサーには意味が判らなかった。
「人間の更正?」
「そうだ。更正させるためには殺すしかない」
しかし、調べてみると、男の容疑は窃盗だった。歯科医宅に侵入してラジオを盗んだのだ。そのことを問いただすと、
「そうさ。ケチな容疑さ。俺は何人も殺しているから、どおってことねえよ」
レッサーは直ちにそのことを報告したが、上司はパンズラムのハッタリだと信じていた。
「あいつはああやって風呂敷を広げることで時間稼ぎしようとしてるんだ」
実際、パンズラムは過去に何度も服役していたが、容疑はいずれも不法侵入や窃盗だった。
10月22日、パンズラムの房が抜き打ちで検査された。鉄格子の1つが緩められている。こんなことを出来るのはパンズラムしかいない。直ちにしょっぴかれ、殴る蹴るの暴行を加えられた上に吊るし刑に処された。両手を背中で縛られて手首から吊るされた状態で12時間も放置されたのだ。
心配したレッサーが様子を見に行くと、床に倒れていたパンズラムは、
「よお、お前さんかい?」
手首の皮膚が裂けている。
「大丈夫か?」
「ああ、これぐらいは慣れっこよ」
ところが、別の看守が房を覗き込むとパンズラムは口汚く罵った。たちまち4人の看守によってたかってボコボコにされた。
同情したレッサーは、信用できる囚人に1ドルを預け、パンズラムに渡すように頼んだ。
「これで何かうまいものでも買うように伝えてくれ」
金を受け取ったパンズラムは冗談かと思った。本心だと知った時、止めどもなく涙が溢れた。人から親切にされたのは生まれて初めてのことだったのだ。
「こういう時になんて云ったらいいのか俺には判らねえ。ただ、あんたにだけは俺のしてきたことを教えてやろう。紙と鉛筆を差し入れてくれないか? そうすれば書いて教えてやれる」
囚人に紙と鉛筆を差し入れるのは規則違反だった。しかし、そうすることでこの男が救われると思った。翌日、レッサーは危険を冒して紙と鉛筆を差し入れた。
カール・パンズラムは1891年6月28日、ミネソタ州の小さな農家で生まれた。6人兄弟の4番目だった。父親は彼が7歳の時に家出した。
パンズラムが初めて警察のお世話になったのは僅か8歳の時だった。酒を飲んで補導されたのだ。そして、11歳で少年院に入れられた。
「そこで俺は人が他人に行うひとでなしの悪行について、たっぷりと教わることとなった」
体罰としてしこたま殴られ、裸で縛りつけられたこともあった。社会に対する激しい憎悪の萌芽がこの時に芽生えた。
その後も窃盗を繰り返し、シャバとムショを何度も行き来していたパンズラムは、1915年にその生涯を決定づける出来事に遭遇する。サンフランシスコで逮捕された時、盗品の隠し場所を吐けば刑を軽くしてやるとの取引を持ち掛けられたのだが、それに応じても刑は軽くならなかったのだ。
「俺は約束を守ったが、判事も検事も守らなかった。あいつらはたっぷり7年もの懲役を喰らわしやがったんだ。ブタ箱に戻った時、看守どもは俺を嘲笑った。堪忍袋の緒が切れたとはこのことだぜ。俺は房から抜け出すと、他の房の鍵穴をすべて埋めてから、辺りのものを手当りしだいにぶち壊した。そして、ガラクタを積み上げてバリケードにすると火を放ったんだ。だが、奴らが突入してきたんで消されちまった」
単なる窃盗犯が全人類への復讐を誓った瞬間である。
それからのパンズラムは事あるごとに反抗し、そのたびに穴ぐらに放り込まれてボコボコにされた。それでも彼はやめなかった。看守の顔に便器の中身をぶちまけたり、食料庫に侵入して盗んできたアルコールを囚人に振るまって騒ぎを起こしたり、囚人仲間の脱獄を手助けしたりした。その追跡の際に、刑務所長が銃撃されて死亡した。パンズラムは狂喜したが、新任の所長は彼を「消火ホースの刑」に処した。我が国でも死者を出した体罰である。それでもパンズラムは耐え抜いた。そして、この体罰が州知事の耳に入り、新所長は免職された。
1917年、チャールズ・A・マーフィーがオレゴン州立刑務所長が就任した。彼は元陸軍大尉にしては珍しくリベラルな人物で、凶悪な囚人でも人として対等に接すればそれに応えてくれる筈だと信じていた。彼と出会ったことでパンズラムの人生に陽が射したかに思えた。ところが、結果としてこのことが裏目に出てしまうのである。