
ヨネを責めた道具
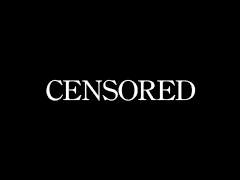
ヨネの無惨な遺体(希望者のみ閲覧可)
大正6年(1917年)3月2日午後5時頃、東京市下谷区龍泉寺町の開業医が、小口末吉(29)なる大工から往診を依頼された。早速、その間借り先を訪ねたところ、内妻の矢作ヨネ(23)が床に伏している。どれどれと布団をめくって仰天した。全身が焼け爛れた上、生傷だらけだったのだ。手足の指も切断されている。
「いったいどうしてこんなことに?」
かく問いただせども末吉は押し黙ったままだ。一応は応急処置を施すも、どう見ても事故とは思えない。犯罪の疑いありとして、医師は警察に通報した。
2日後に死亡したヨネは、それは酷い有り様だった。臀部や大腿部に22ケ所、陰部にも左右3ケ所ずつの傷が並んでいた。背中と右腕の3ケ所に焼け火箸で「小口末吉妻」と彫られている。左足の薬指、右足の中指と小指がなく、左手の薬指と小指も第二関節から切断されていた。
当初の時点では、嫉妬に狂った末吉の一方的な犯行と思われていた。3月4日付の『読売新聞』にはこうある。
「末吉は生来残忍なる上、嫉妬深く、かつて為せるヨネの不始末を思い出すごとに常に手酷くヨネを責め…四肢を細紐にて縛し、手拭いにて猿ぐつわをはめたる上、刃物にて両足親指を切断したるを手始めに…焼け火箸にて背部に『小口末吉妻、大正六年』と烙印したるなど、残忍極まる凶行に出で、ヨネは今日まで生き地獄にも等しき苛責のもとにありたるものと判り」
しかし、解剖を担当した医師は、単なる折檻死ではないことに気づいた。ヨネに刻まれた傷は前と後ろがほぼ相対しており、陰部の傷も左右対称なのだ。ヨネの協力なしに、このような整然とした傷痕になるだろうか?
また傷は長期に渡るものであるにも拘らず、ヨネは逃げ出しもせず、医者にも風呂にも通っていない。
つまり、ヨネは傷を負うことを望んでいたわけで、マゾヒストだったのではないかと思われるのだ。末吉の供述もそのことを裏づけている。
「これらの傷はみなヨネがつけてくれと云うからつけました。嫌だと云えば、別れると云う。別れるのは困るから、云われるままつけてやりました」
末吉とヨネが出会ったのは大正2年2月頃、浅草千束町でのことである。ヨネは吉原で女中をしていたとも、おでん屋の屋台を出していたとも云われている。末吉によれば、誘って来たのはヨネだという。
「大工さん、活動に行こう」
妻子のいる末吉は最初は断ったが、ヨネはなおも誘ってくる。据え膳食わぬは男の恥。共に活動写真に出掛けた後、木賃宿で結ばれた。
「泊まれと云ったのは向こうです。銭は向こうで出してくれました。その時は二つしただけです。私は一つしたら嬶のことを考え、嬶に済まないと思って止めようとしたら、女がしようというので二遍しました。その時の色に変わったことはありませんでした。その後、時々、方々でその女と色をしました。それから一緒になりました」
末吉が妻子を捨てて、今戸町の雑貨屋に間借りしてヨネと暮らし始めたのは同年12月のことである。ところが、間もなくヨネが隣の部屋に間借りする男と密通していることが発覚する。末吉は相手に手切れ金を払って別れさせ、下谷区龍泉寺町に引っ越すも、ヨネの浮気癖は相変わらずだった。そして、そのたびに末吉に詫びて、思う存分責め苛んでくれと哀願したという。
思うに、ヨネには折檻願望があり、浮気は折檻を引き出すだめの口実だったのではないだろうか。
一方、末吉は、精神鑑定によれば「性格は愚鈍で、判断力は普通人より乏しい」とのことで、深く考えず、云われるままに折檻していたのだろう。末吉をサディストと見る向きもあるが、私にはそうは思えない。末吉にはサディスト特有のギラギラしたものが感じられない。
「妻の身体に傷をつけたのは警察に来る1ケ月余り前のことです。何処へ行って死んでもあなたの女房だと云うので、焼け火箸でその背中に私の名前を書いたのです。小口末吉と書いたのです。しかし、背中では自分で見ることが出来ないと云うので、次に手にまた焼け火箸で名前を焼きつけたのです」
「どうしてそんなものを書く気になったか、と妻に訊くと、これを見て他の男には決して心を動かさぬためだと云うから、そんなら一つ書いてあったらたくさんではないか、と云ったら、最初腕を上げて書いてもらったので、腕を下げると逆さになって困る。それで書き直して欲しいと云う。なるほどと思って、今度は腕を下げさせて書いてやりました」
「二、三日すると、腕の外側にばかり書いてあるので、寝ていて見ようとしても何も見えない。寝ていても見えるように書いてくれと云う。なるほどと思って、今度は腕の内側に書いてやりました。これで3通り書いたことになりました」
この「なるほど」の部分に末吉の愚鈍さが窺える。
ヨネはさぞ熱がったろうと取調官が訊ねると、
「ヨネは傷つける時、一度だって痛いなんて云ったことはありません。焼け火箸をつける時は、手拭いをかたくくわえて我慢して、熱いなんて云ったことはありません。大きな灸よりも楽だと云っていました」
ヨネが真性のマゾヒストであることを物語るエピソードがある。或る元旦のこと、ヨネは半紙に「マオトコシタ セケンノカガミ」と書いて自分の背中に貼りつけ、末吉と共に吉原界隈を練り歩いたというのだ。その際、末吉はヨネにせがまれて「ブッカラ、チャッカラ」と囃しながらヨネの前を歩いた。やがて子供たちが面白がり、ゾロゾロとついて来たので切り上げたという。
笑われたろうと取調官が訊ねると、
「私どものすることですから、見る人には関係ないのです。笑わなくてもいいでしょう」
つまり、これもプレイの一環なのだ。見せしめを終えたヨネは、興奮して激しく求めて来たという。かなりの淫乱だったようだ。
「だいたい女の方からするのです。晩に三遍か四遍は欠かしません。寝ると直ぐにして、眠りに就く時また一遍する。私は身体が変になると云って断っても承知しません。ちんぽが立たなくなると、いじって無理に立たせるのです。夜明け時分にまたして、朝飯を拵えて、食べると云うて起しに来て、起きようとする時にまた布団の中に入って来てすることもある。起きてからすることもある。それは飯を食っている時に、前をまくって私のところにいつかるのです。一日に三遍も四遍もするのです」
「いつかる」とは「乗っかる」という意味らしい。ヨネは専ら女性上位を好んだようだ。
「死ぬ二ケ月も前、正月から私のをしゃぶるのです。色のあとに拭けと云っても、あなたと二人のだから拭かぬのだと云うて、舐めて直ぐまた入れるのです。私はくすぐったいので嫌だと云いました。私にも舐めろと云うたが、私は嫌だと云ったら、それでは惚れたのではない別れる気だと云うので、別れては仕様がないから私も舐めちまいました。二遍ほど舐めました。その他に別に変わったことはありません。ぶち合ってしたことはある。色をしながら飯を養って食わしてくれたこともある。私は人が来てはいかぬからと云ってもきかないのです」
二人のプレイは次第にエスカレートして行く。
「色をしながら傷をつけることはありませんが、色をしてから後で傷をつけたことはあります。色をしてからすぐに指を切ったこともあります。左の小指を切った時は色をして直ぐでした。私が小便に行っている間に指を切ったので、帰って来てから膏薬を貼ってやったら、直ぐ寝ろと云うので寝たら、私のちんぽを舐めて立たしてはめたのです。それであんた別れないんだろうねと云いました」
当初、ヨネは右手の小指を切ってくれと頼んだという。これを受けて末吉は「右手は色々と使うことだから、右手だけはよした方がいい」と説得し、ならば左手だということになったらしいが、その前に指を切ることを止めようよ。
指を切る際、ヨネは自ら俎板の上に指を乗せて、ノミで切りにかかった。ところが、非力さゆえになかなか切れぬ。血がだくだくと流れるのみである。そこで末吉に切ってくれと哀願する。仕方がないので、金槌でノミを叩いて切断した。
「指はポーンと飛びました」
足の指はヨネが自分で切断した。その後、末吉に「先に寝ろ」というので寝ていると、ヨネが乗っかって来たという。末吉は「臭くて嫌だ」と断った。その頃のヨネは体中が傷だらけ膿みだらけで、おまけに長いこと銭湯に行っていなかったので悪臭を放っていたのだ。ヨネはそれでもすると云って聞かず、太腿を切ってくれと哀願した。末吉が断ると「切らないのは別れるつもりだろうから、もう死んじまう」などと云い出すのだから困ったものだ。仕方なく合い口で斬りつけると「今度は足だ」と自ら切りつけたという。そんなこんなの繰り返しで死んじまったというわけだ。
性科学者の高橋鐵は「ヨネは最初からマゾヒストではなく、サディズムが先行していた」として「判明する事は、ヨネの飽くなき性交欲で、軽微なサディズムは予備快感(前戯)に用い、しかも満たされない欲情は猛烈なマゾヒズムで満たしていた事実である」と分析している。なるほど。私もそう思う。ヨネは末吉を困らせることに悦びを覚えていたとも見受けられるからだ。
哀れなるはヨネに振り回された末吉である。しかし、彼が罪に問われることはなかった。判決を前にした大正7年9月23日に、恰もヨネの後を追うかのように、脳溢血でポックリと逝ってしまったからだ。
割れ鍋に綴じ蓋の夫婦は、あの世でもプレイを楽しんでいるのだろうか?
(2009年6月11日/岸田裁月)